「魔の2歳児」と言われる時期に限らず、子どもが突然大声で泣いたり、物を投げたりする“癇癪(かんしゃく)”。
どう対応すればいいのか悩んだパパも多いはずです。
僕自身も、戸惑いながら少しずつ対応のコツをつかんできました。

この記事は、こんな人におすすめ!
- 癇癪が始まるとどう対応していいか分からない
- パパなりにできる癇癪対応を知りたい
- 子どもの気持ちの寄り添う関わり方を増やしたい
今回は、そんな僕が実際に試して効果を感じた「癇癪対応の5つの工夫」をご紹介します!
子どもの癇癪ってなぜ起こるの?

まずは、そもそもなぜ癇癪が起こるのかを理解するところから始めましょう。
「ダメ!」と怒る前に、その背景を知ることで関わり方も変わってきます。
成長の一環としての「自我の芽生え」
子どもが癇癪を起こすのは“わがまま”というより「自分の意思がはっきりしてきた証拠」です。
自分でやりたい気持ちが育ってきたのに、うまくできない。その“もどかしさ”が爆発する瞬間です。
僕自身、最初は「ただのワガママかな?」と思っていました。
でも“癇癪”という言葉を知ってからは、ただ困らせたいわけではなく「伝えられない感情が爆発してるんだ」と理解できるようになりました。
「やりたい!」「こうしたい!」という気持ちと、現実とのギャップにイライラしてしまうんですね。
これは、心が成長している証でもあります。
言葉でうまく表現できないフラストレーション
まだ言葉がうまく使えない子どもは、自分の気持ちを伝える手段が限られています。
その結果、泣いたり怒ったりすることで自分の感情を表そうとします。
「これ、なに言ってもダメそうだな…」という瞬間、ありますよね。
泣きわめく子どもに何を言っても響かない。
やってはいけないことは、子どもの泣き声より大きな声で「どうしたの!?」と声をかけてしまったこともありますが、逆効果でした。
どんなに優しい言葉でも“声が大きい”と火に油。余計に癇癪が収まらなくなるのを体感しました。
大人のように理性で抑える力が未熟だからこそ、癇癪という形で爆発してしまうのです。
パパが試して効果のあった対応5選

では、実際に僕が家庭で試して「これは効果があった」と感じた癇癪対応を5つ紹介します。
子どもの性格によって相性はありますが、どれも簡単に試せる方法です!
① 落ち着くまで“そっと見守る”
つい「やめなさい!」と言いたくなる癇癪。でも、逆効果なことが多いです。
まずは落ち着くまで無理に関わらず、ただそばにいることにしました。
その場から離れず“安全を確保しながら見守る”ことが一番効いたパターンもあります。
泣くのは子どもの“仕事”くらいに思って、「おつかれさま」と声をかけるような気持ちで接しています。
時と場合にもよりますが、他の人の迷惑になりそうな場所ならその場から離れてから見守るようにしています。
② 気持ちを“言語化して代弁”する
子どもは思ったことを言語化することがまだ難しいときがあります。
「これが欲しかったんだよね?」「これじゃないの?」「あー違うか、ごめんごめん」など1つずつ聞いてみるのもありです。
うまく当たると、ピタッと泣き止むこともあって「これか!」という瞬間が嬉しかったり。
子どもの気持ちを代弁することで、驚くほど落ち着く場面がありました。
自分の感情を理解してもらえたと感じることが、癇癪の沈静化につながるようです。
③ “抱っこ”で安心感を与える
言葉よりも“抱っこ”が効くときもあります。
抱っこができるタイミングなら積極的に。
我が家では、癇癪を起こした相手と違う人に抱っこされると落ち着くこともあり、うまく夫婦で役割を切り替えながら対応しています。
ただ癇癪中に抱っこしようとすると逆効果なので、子どもが暴れ終わったタイミングで、無言でぎゅっと抱きしめる。
それだけで安心してスーッと落ち着くことも少なくありません。
④ 親も“深呼吸”して冷静になる
癇癪は親の感情もゆさぶりますよね。
僕は、「怒らず、まず深呼吸」を意識するようにしました。
癇癪に合わせて怒ったところで、悪くなることはあってもよくなることは決してありません。
子どもにとっても、パパの落ち着いている姿を見ることは“安心材料”になります。
癇癪したときの実体験としてパパがやったこと、やらなかったことは【癇癪が起きたとき、パパがまずやったこと・やらなかったこと】にまとめました。
⑤ 癇癪が収まった後の“フォロー”を大切に
癇癪が落ち着いた後こそ、親子の関わりが大切です。
泣き止んだ後、「○○が嫌だったんだよね。気づけなくてごめんね」と言葉をかけるようにしています。
ここでちゃんと“気持ちに共感したよ”と伝えることで、次の癇癪の回数が減るような気もしています。
「怒られなかった」という安心感が、次の行動にもつながります。
癇癪に向き合う中でパパが感じたこと

試行錯誤しながら癇癪と向き合ってきた中で、僕自身もたくさんの学びがありました。
最後に、実践して気づいたことを少し共有します。
「正解」がないからこそ、試してみる
癇癪の対応に“絶対的な正解”はありません。
癇癪には“正解”がありません。子どもの気質や、その日の体調、機嫌によっても対応が変わります。
だからこそ、いろんな方法を試して“我が家に合う対応”を見つけるのが大事。。
実際にパパが試して効果があった声かけは【「なんで泣いてるの?」から脱出!癇癪に効いた声かけと言葉】で紹介しています。
子どもとの信頼関係を深めるチャンスにも
癇癪はしんどい時間ですが、「わかってくれた」と子どもが感じられれば、信頼関係が深まります。
「この子、今伝えたくても伝えられないんだな」と思えるようになると、関わり方も変わります。
気持ちを理解しようとする姿勢が、子どもに安心感を与えるんだと感じています。
実際、落ち着いたあとに「パパ、ごめんね、ありがとう」と言ってくれたときは成長ぶりに泣きそうになりました。
まとめ
癇癪は、子どもの心が成長している証であり、親にとっても大きな試練です。
けれど、対応の仕方ひとつで、お互いの気持ちが少しずつ通じるようになります。
今回紹介した5つの工夫は、どれも“完璧じゃなくてもできること”ばかりです。
毎回うまくいかなくても大丈夫。子どもと向き合い続けるパパの姿勢が、何より大切な“対応”なのかもしれません。
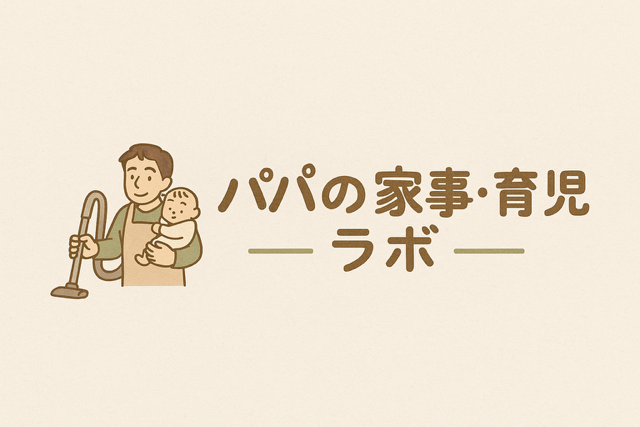

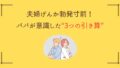

コメント