おもちゃを片づけたら大泣き、服を着替えるだけで全力拒否。
子どもが突然スイッチが入ったように怒りだす「癇癪(かんしゃく)」に、どう対応すればいいのか…悩むパパは多いはずです。
わが家でも最初はあたふたし、「なんでそんなことで!?」とイライラしてしまうこともありました。
でも、癇癪に向き合ううちに気づいたのは、「やること以上に“やらないこと”が大事」ということ。

この記事は、こんな人におすすめ!
- 子どもが泣きわめいているとき、どう対応すればいいのかわからない
- つい無視したり、問い詰めたりしてしまうのを減らしたい
- 落ち着いた後に、どう声をかけるのが正解か知りたい
今回は、実際に我が家で試して効果があった対応と、逆効果だった対応をリアルに紹介します。
パパが癇癪対応で意識した3つのこと

癇癪の対応って、「正解がない」からこそ難しい。
でも、いくつかの場面を経験するうちに、うまく乗り越えられたときに共通する“対応のクセ”が見えてきました。
ここでは、「やったこと」と「やらなかったこと」をセットで振り返ります。
パパだからこそできた、感情に振り回されないコツを参考にしてもらえたらうれしいです。
1. まず“手を止めて向き合う”/やらなかったこと:無視する
癇癪が起きた瞬間、真っ先にやったのは「手を止めて、子どもの前にしゃがんで向き合う」こと。
泣き声や怒りの声に対してすぐ何か言いたくなるけれど、まずは“気持ちを受け止める姿勢”を見せるようにしました。
一方で、やらなかったのは「完全に無視する」こと。
確かに放っておいたらおさまることもありますが、何度かやった結果、子どもが“見てもらえなかった悲しさ”を引きずる様子も。
無視ではなく、少しだけ間をあけてでも向き合うようにすることで、子ども自身も「気持ちを出していい」と安心できたようです。
2. 感情を言葉にしてあげる/やらなかったこと:理由を問い詰める
癇癪中の子どもに「どうして怒ってるの?」と聞いても、うまく答えられないのが現実。
だから、パパが代わりに「〇〇がイヤだったんだね」「自分でやりたかったんだよね」と気持ちを代弁してあげるようにしました。
これが意外と効果的で、「うん!」とうなずいて落ち着くことも。
逆にやらなかったのは、「なんでそんなことで泣くの?」「いいかげんにして」と問い詰めたり説教すること。
癇癪中は話が通じないことがほとんどなので、理由を聞こうとするより、共感ワードで寄り添うほうが結果的にスムーズでした。
癇癪に効いた声かけは【「なんで泣いてるの?」から脱出!癇癪に効いた声かけと言葉】で紹介しています。
3. 落ち着いた後に一緒に“修復”する/やらなかったこと:すぐ切り替えさせる
癇癪がおさまった後、「もう泣かないでね」と流してしまいがちですが、その後のフォローこそ大事。
我が家では、「さっきは嫌だったね」と改めて気持ちを振り返ったり、「パパもびっくりしちゃった」と自分の気持ちも伝えるようにしています。
そして「どうすればよかったかな?」と一緒に考え、親子で“感情の整理”をする時間を大切に。
逆にやらなかったのは、「もう終わったから遊ぼう!」とすぐに話題を変えること。
もちろん切り替えも大事だけど、子どもは“ちゃんと気持ちをわかってもらえた”という実感がないと、同じことを繰り返しがちです。
【まとめ】
癇癪への対応は、正直その場その場で正解が違います。
でも、実際にやってみて効果があったのは、「どう関わるか」よりも、「どうしないか」を意識することでした。
怒ったり責めたりするよりも“受け止めて、寄り添う”というスタンスを持つことで、子どもの癇癪は次第に落ち着いていきました。
パパだって、いつも冷静ではいられません。
でも、「この子なりの理由がある」と思えるだけで、ぐっと対応が変わります。
この記事が、あなたの“次の癇癪タイム”を少しでもラクにするヒントになればうれしいです。
実際にパパがやって効果があった癇癪対応は【子どもの癇癪(かんしゃく)にパパが試して効果あった対応5選】でも紹介しています。
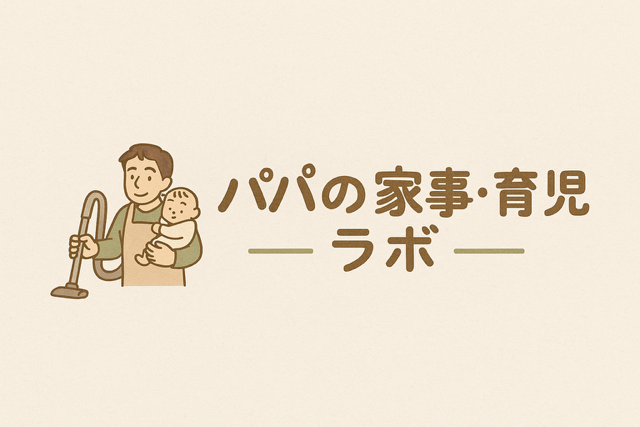



コメント